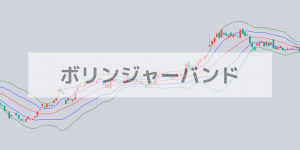一目均衡表とは?基本的な使い方について徹底解説!!

目次
1.一目均衡表の基本的な概念
一目均衡表とは何か?
一目均衡表とは、日本のトレーダーである細田悟一が考案したテクニカル分析の一つです。
価格のトレンド、トレンドの転換点、サポートラインやレジスタンスラインを視覚的に捉えることができるトレンド分析手法です。
一目均衡表の特徴
一目均衡表は、5本の線と時間論・波動論・値幅観測論の3つの理論から構成されており、ロング・ショート共に細かな分析ができるトレーダーの中でも人気のあるテクニカル手法です。
2. 一目均衡表の構成要素
一目均衡表の構成要素
一目均衡表は、以下の5つの線で構成されています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 転換線 | 過去9日間の最高値と最安値の平均値を求めて算出されます。短期の値動きを把握するために用いられます。 |
| 基準線 | 過去26日間の最高値と最安値の平均値を求めて算出されます。中期的な値動きを把握するために用いられます。 |
| 先行スパン1 | 転換線と基準線の平均値を求めたものを、未来に26日分ずらした(予測した)ものです。この値が、未来の価格のサポートやレジスタンスとして機能します。 |
| 先行スパン2 | 過去52日間の最高値と最安値の平均値を求めたものを、未来に26日分ずらした(予測した)ものです。この値も、未来の価格のサポートやレジスタンスとして機能します。 |
| 遅行スパン | 現在(当日)の終値を、過去に26日分ずらした(遅行させた)ものです。この値が、最も重要でサポートやレジスタンスとして機能します。 |
3. 一目均衡表の使い方
トレンドの確認
転換線や基準線、そして先行スパン1と先行スパン2の位置関係により、トレンドが上昇傾向、下降傾向、またはレンジ相場かどうかを判断することができます。
転換線や基準線の上に株価が推移していれば上昇トレンド、下に株価が推移していれば下落トレンドとなります。
なお、一目均衡表が活躍する時間足は基本的に日足です。
先行スパン1と先行スパン2の間の雲によるトレンドの判断
先行スパン1と先行スパン2の位置関係により、間に存在する雲からトレンドを判断することもできます。
例えば、ローソク足が雲の上に位置していれば上昇トレンドとなります。
また、ローソク足が雲の中にいて、その雲を上抜けする際は強い買いシグナルとなります。
これは逆も然りで、雲の厚さが厚ければ厚いほど相場の反転は難しくなります。
サポートライン・レジスタンスラインの設定
転換線や基準線、先行スパン1や先行スパン2がサポートライン・レジスタンスラインとして機能することがあります。
これらのラインを利用して、サポートラインやレジスタンスラインを設定することができます。
転換線と基準線のクロスによるシグナルの判断
転換線と基準線がクロスするポイントにより、相場の転換シグナルを判断することができます。
転換線が基準線を上から下にクロスする場合、売りのシグナルとなります。
逆に、転換線が基準線を下から上にクロスする場合、買いのシグナルとなります。
4. 一目均衡表のトレード戦略
基準線クロス戦略
一目均衡表において、転換線が基準線をクロスし上抜けた場合は買いのシグナル、下抜けた場合は売りのシグナルと判断することができます。
このトレンドの方向に合わせて、投資を行うことで上手くトレンドフォローをすることができます。

雲を使ったトレード戦略
雲の上に価格がある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドと判断することができます。
また雲を上抜けた場合は上昇トレンドの開始と判断し買いシグナルと判断することもできます。

5.一目均衡表を使ったトレードでよく起こる誤解
トレンド転換の遅延性によるリスク
一目均衡表は、トレンドの転換を予測することができる優れたツールです。
しかし、転換が確定するまでに時間がかかるため、トレンド転換の遅延性によるリスクがあります。
つまり、トレンドが既に転換してからシグナルが現れるため、遅れてエントリーやイグジットを行ってしまう可能性があるということです。
他の技術分析指標との組み合わせの重要性
一目均衡表は、他の技術分析指標と組み合わせることで、より精度の高いトレードシグナルを生成することができます。
例えば、一目均衡表とRSIを組み合わせることで、より正確なエントリーやイグジットのタイミングを把握することができます。
ただし、過剰な指標の使用や、指標の相関性に注意することも重要です。